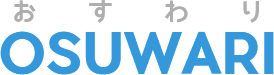腫瘍とはどんな病気なの?

腫瘍と呼ばれるものには「悪性腫瘍」と「良性腫瘍」とがあります。ガンと呼ばれるものはこの「悪性腫瘍」をいい、たちが悪いものは、手術しても他の場所に転移し、再発を繰り返すことです。
ガンの種類は多種多様にわたりますが、一般的には皮膚の上にできた腫瘍の80%が良性で、手術で除去が可能だということです。
8歳以上の高齢の犬であれば、こうした腫瘍やがんにかかる可能性が高くなる傾向にあります。
腫瘍の症状はどんなものがある?

できる部位によって症状はさまざまですが、飼い主が目視できることとして、特に皮膚や皮膚の下にしこりができていることが多く、だんだんと大きくなってくる、形が変化してきたなど異変を感じることが多いでしょう。
また、体内にできる腫瘍の場合「痩せてくる」「発熱がある」「ふらつきや貧血がみられるようになった」「リンパ節が腫れてきた」などもわかりやすい症状です。
皮膚にできる腫瘍の場合
胸部、腹部、ワキの下、股下などに発生することが多く、歩き方の異変で気が付くことが多いでしょう。皮膚にできた傷と間違うこともありますが、かさぶたができている、傷が大きくなる、できものが膨らみ、変形してくるなど、目で見て気が付くことも多いです。
肛門周り、耳の中、瞼、指の間など粘膜や皮膚の柔らかい部分に発生することも多いです。
乳腺にできる腫瘍
胸、ワキの下、腹部、股下にしこりができることで気が付くことが多いです。
腹部にできる腫瘍
主に消化器、腎臓、膀胱、肝臓、子宮などの腹部の臓器にも腫瘍ができることがありますが、体内にできる腫瘍は発見が遅れることが多く、治療が遅くなることが多いです。
嘔吐や下痢が続く、排便、排尿障害、体重が減る、腹部が膨張するなどが主な症状です。
悪化すると貧血なども起こすことがあります。
口腔内にできる腫瘍
歯茎が盛り上がって見える。
口の粘膜や舌に黒い腫瘍がみられるようになり、急激に大きくなることがあります。
骨にできる腫瘍
大型犬に多く発生します。骨の腫瘍は2歳前後の若い犬でもかかりやすい病気です。
外傷や捻挫がないのに、足を引きずる、足が腫れるなど、歩行障害が起こることがあります。
腫瘍の原因はなに?予防はできるの?

腫瘍の原因は様々です。化学物質やホルモン、ストレス、遺伝、ウィルスなどといわれることもありますが、ほとんどの場合、原因を特定することは難しいといわれています。
ガンを発症するまでのメカニズム
ガンを発症するメカニズムは健康な犬にも存在しています。ガンを発症しないのは、体内のリンパ球が、ガンを排除する働きをしているから、健康な体を保つことができるのです。
こうしたリンパ球などは「免疫機能」と呼ばれ、体内に異物やウィルスが入った時に、排除し、体を守ってくれる防御隊のような役割を果たしています。
こうした健康な体を維持するためには、自律神経の働きが不可欠です。交感神経と副交感神経が正常に働いているから、自律神経のバランスを保ち、免疫機能を低下させずにいられるのです。
この自律神経のバランスが崩れる最大の理由は「ストレス」です。ストレスがかかると、交感神経と副交感神経の交換がうまくいかなくなり、免疫力が低下し、リンパ球が少なくなってしまうのです。
原因① 食事
ペットフードには様々な栄養が含まれており、愛犬に手軽に与えることができる食事の一つです。これらの中には添加物や廃棄原料を含んでいる食品も多く出回っています。
愛犬の健康維持のためにも、しっかりとしたメーカーの製品を選び、「無添加」のフードを選ぶようにしましょう。
また、水道水には発がん性物質が含まれています。ミネラルウォーターや浄水器の水、または、一度煮沸した水を飲ませるなど、飲料水にも注意が必要です。
原因② 運動不足
人間にとって便利になった社会には、自然のように犬が自由に動ける場所が少なくなり、運動不足の犬もすくなくありません。ストレスを発散させるためには、定期的な運動が必要です。毎日の散歩は、運動だけでなく、犬にとっての自然の感覚を取り戻すのには非常に大切です。外の匂いで犬は情報を得ます。ほかの犬の行動などの情報収集を行い、本能を取り戻す行動が散歩には含まれているのです。
原因③ 犬と人との暮らし
屋外犬は、飼い主と離れて暮らすため、外的ストレスだけでなく、心理的なストレスも少なくありません。犬は元来群れで生活をしている動物です。できるなら、室内で飼育するほうが犬にはストレスがかからないでしょう。その際には、犬の身体の大きさにあったゲージや、エアコンなどを利用し、快適に過ごせる工夫をしましょう。
屋外でも犬にストレスがかからず、安心して過ごせるような配慮が必要です。
また、正しくしつけを行い、飼い主との主従関係を知ることで、犬もストレスなく過ごすことができます。
腫瘍にはどのような種類がありますか?
犬の腫瘍(ガン)の種類は多岐にわたります。
- 皮膚にできる腫瘍(ガン)
- 乳腺腫瘍、皮膚の腫瘍、脂肪腫、扁平上皮ガン
- 分泌腺・細胞の腫瘍(ガン)
- 腺腫、腺ガン、肥満細胞腫
- 内臓の腫瘍(ガン)
- 腹部の腫瘍、平滑筋腫、胃ガン、直腸ガン、肝臓ガン、腎臓ガン、卵巣ガン、子宮ガン、口腔内の腫瘍など
- 骨の腫瘍
- 繊維肉腫、骨の腫瘍、骨腫、骨肉腫、軟骨肉腫、リンパ腫
治療方法はどのようなものがありますか?

愛犬に腫瘍(ガン)が見つかった時には、どのような治療方法があるのでしょうか?
それぞれの治療方法のメリット、デメリットについてまとめてみました。
1.手術
外科手術で、がん細胞や腫瘍が発生している部位を取り除く方法です。
<メリット>
- 手術によって大幅に罹患部分を除去できる。
- 副作用が少ない。
- 短時間で済む。
<デメリット>
- 手足や顎などを切除、切断した場合、外見が損なわれるばかりでなく、運動機能にも支障をきたす場合がある。
- 麻酔や手術後に合併症を引き起こし、症状が重篤化したり、死亡したりするケースもあります。
2.薬物療法・化学療法
ガン細胞だけをターゲットに抗がん剤を投与し、治療を行います。抗がん剤により、がん細胞や腫瘍の分裂・増殖を抑えることができます。
<メリット>
- 愛犬の生活の質を落とすことなく過ごすことができる。
<デメリット>
- この化学療法だけでは根治が難しいといわれています。
- 脱毛などの副作用がみられることもあります。
3.放射線療法
ガンや腫瘍のある場所に体内、体外から放射線を照射します。
<メリット>
- 細胞分裂が盛んなガン細胞に効果が高い。
- 脳や心臓など手術しにくい部分などに対応できる。
<デメリット>
- 全身麻酔が必要で、コストがかかる。
4.免疫療法
体内にある免疫機構を、癌細胞に向けて得意的な攻撃をするように作用させる治療法です。
<メリット>
- 治療後体内に残った腫瘍を根絶するための効果が高い。
- 副作用が少ない
<デメリット>
- 研究開発段階の治療の場合があり情報が不足していることがあります。
5.代替療法
マッサージ、バーブ、鍼灸などをつかい、血流促進し、自然免疫力を高める方法です。
<メリット>
- 飼い主も愛犬に行うことができる。
<デメリット>
- 専門家に指導を受けないと効果がないものになる可能性もあり、取扱いに注意が必要。
- 即効性がなく、明確に効果がでるか不明。
6.食事療法食
食事療法食は単体での治療ではなく、あくまでも他の治療法と併用でおこなうものです。とはいえ、愛犬が病気をしっかり治して健康な体になるためにも適切な食事はかかせません。
犬の病気の進行具合や治療法によっては、これまでどおりの食事がとれるようになるまで時間がかかりますし、それまでのドッグフードを与えて良いのか不安を持つことが多いことでしょう。
食事によってがんや病状が進行したり治療の経過に影響を及ぼすことはありませんが、元気になって欲しいのに食が進まなくて悩んだり、弱ったの免疫力を高めるような食事を食べさせたいと思うのは、飼い主ならば当然です。
そんな飼い主さんの悩みに答えるように、最近では療養中のワンちゃん向けに作られた療養ドッグフードが開発されました。がん細胞や腫瘍への栄養を絶ち、犬の免疫力をキープしてくれる安心の犬専用の療養食です。
療養食で悩んでいる方は、そういったドッグフードを利用するのもオススメです。
家庭でできるケアについて
腫瘍やがんは犬も人間同様、早期発見が必要です。
予防や早期発見のポイントについてまとめました。
- 愛犬の様子がいつもと違うと思ったら、すぐに獣医師に相談しましょう。
- 毎日のスキンシップで、におい、おでき、しこりなどを確認できます。
- 食事の安全面、適度な運動をこころがけるようにしましょう。
- メス犬の場合、子宮や乳腺の腫瘍、ガンを予防するためにも避妊手術を行いましょう。
また、もし腫瘍が見つかった場合は獣医師に相談し、完全に治るまで治療を続ける「根治治療」を目指すのか、痛みや苦痛を和らげる「緩和治療」にするのかしっかり相談し、治療をどこまで行うかをしっかり検討する必要性があります。
もし、治療と並行して、家庭でできるケアを考える場合にも、獣医師に相談し、間違ったホームケアをしないようにする必要があります。